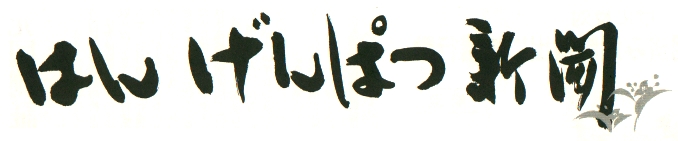西尾漠(『はんげんぱつ新聞』編集長)
高レベル放射性廃棄物の処分方法は、いまは深地層への埋設=地層処分の方針とされているが、それは、かつては否定されていた方法だった。
原子力委員会の廃棄物処理専門部会が1962年4月にまとめた中間報告書では、最終処分方式として「深海に投棄すること」と「土中に埋設したり、天然の堅牢な洞窟あるいは岩石層に入れること」の2方式を挙げたうえで、「国土が狭あいで、地震のあるわが国では最も可能性のある最終処分方式としては深海投棄であろう」とされていたのだ。
『原子力バックエンド研究』24巻2号に掲載された「地層処分概念開発史」で、動力炉・核燃料開発事業団・核燃料サイクル開発機構で一貫して高レベル放射性廃棄物の地層処分研究に従事してきた増田純男原子力安全研究協会参与は言う。
「当時の国レベルの検討の記録には、『地層処分』の語は見当たらず、また地層処分とみなされる概念やそれに類似した考え方が議論された経緯もないことから、地層処分という選択肢は検討の対象にはなかったものと考えられる」。
前出2方式の後者が「類似した考え方」に見えなくもないが、それはさておき、第1候補の深海投棄についてはしっかり研究していたかというと「低レベルの海洋投棄はある程度研究が進みましたが、高レベル処分についての研究実績というのは調べてみてもほとんどありません」というのが実態だったらしい。坪谷隆夫編『オーラル・ヒストリー~地層処分研究開発~』OFFICETSUBOYA発行、http://www.aesj.or.jp/~snw/img/ChisouShobun-oral-history1.pdf)での増田参与の言である。
まごまごしているうちに、その高レベル放射性廃棄物の深海投棄も、1972年12月に採択され、75年8月に発効した「廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約」(ロンドン条約 )によって禁止されてしまう。増田参与の言の引用を続けよう。
「それで日本でも慌てて専門部会が招集されて、先程坪谷さんが言われた1976年ですから、つまりロンドン条約が発効してわずか1年後、『放射性廃棄物対策についての原子力委員会決定』というのが初めて出されて、そこで高レベル放射性廃棄物はガラス固化し30年から50年間貯蔵した後に処分することとして、地層処分に重点を置いた研究を動燃が行うこととする、ということになり、動燃に廃棄物対策室ができました」。
深海投棄禁止に慌てて「わずか1年」で、つじつま合わせすらせずに方針転換が行なわれたということである。
1976年10月に原子力委員会が示した方針では増田参与の言う通り、海外各国に歩調を合わせて「当面地層処分に重点を置き」と変わる。それでもなお「我が国の社会的、地理的条件に見合った処分方法の調査研究を早急に進め」とも書かれていた。翌77年4月、日本原子力産業会議の高レベル放射性廃棄物処理・処分検討会の中間とりまとめも強調する。「高レベル放射性廃棄物管理に関するわが国の対応策は、厳しいわが国の社会条件、自然条件等の諸要因を考慮すると、処理についても、処分についても諸種の幅広い可能性を探求して、わが国に最も適した体系に組み立てていくといういわば『道無き道を推し進む』作業が想定され、柔軟な対応の仕方が要請される」。
しかし、何らの具体的な検討もなく、地層処分が唯一の方針となっていく。ただし、その中でも当初計画は変更を迫られた。
当初は、処分場のサイトをまず選び、そこに適した処分システムをつくるという「今考えればとんでもない計画」だったと増田参与。そのためにボーリング調査を各所で行なうようになり「だんだん社会問題を引き起こすようになってきたようです」と。「地層処分概念開発史」では「地点絞り込み方式は、1984年時点で隘路に入り込み、以降それ以上の進展を見ることはなかった」と述べている。
その隘路からどう抜け出したのか。「オーラルヒストリー」に戻って、長い引用を続けよう。
「その頃に、科学技術事務次官をされていた石渡鷹雄さんが副理事長として動燃に来られて、『今日本で進めている地層処分研究のやり方として、本当に地層を探すことが先なんだろうか』と、まぁ、こんなことをおっしゃられていました。私はその少し前に、カリフォルニア大学(UC)バークレー校のトーマス・ピグフォード先生のところで地層処分の性能評価を研究していましたので、石渡さんからの問いに対して何かメモをつくれといわれ、思いつきのメモを書いて石渡さんに説明に行きました。
その頃、1980年代の中頃ですけれど、当時、アメリカでは、NAS(全米科学アカデミー)が、通称ピグフォード・レポートと呼ばれている『放射性廃棄物の隔離システムの研究報告書』を出していました。
1983年にそのレポートが出された直後、その年の10月頃から1年間、当時東京大学の助教授だった鈴木篤之先生が『エネルギーレビュー』誌に10回にわたってレポートの開設記事の連載をされました。単なる翻訳でなく考察を加えた記事であり、私も大変興味深く読みました。そこには非常に魅力のあることがたくさん書いてありました。単に地質環境に捨てるのではなくて、自然の地質環境には本来的にものを閉じ込める力、包蔵性能があるのでそれに依存するのが地層処分概念の基本である。ただ、処分地によってそのような性能には若干差があるから、それを補い廃棄物の隔離性能をさらに確かなものにするために、その処分地の特性に合わせて工学バリアを設けて多重バリアを設計することができる、ということでした。
[中略]私は処分地選定の前にすることは、多重バリアシステムの性能に着目した研究である、というようなことを申し上げたところ、石渡鷹雄副理事長が、『どうも、俺もそういうことではないかと思っていた』と言われて、動燃の中で若い人が集まって勉強会が始まりました」。
地層処分を研究していた学者らから反発や批判があったものの、日本で地層処分を進めるには都合の良い考えとして徐々に定着する。増田参与が核燃料サイクル開発機構特任参事として統括した「わが国における高レベル放射性廃棄物地層処分の技術的信頼性-地層処分研究開発第2次取りまとめ-」(1999年)は、「わが国の地層処分概念は『安定な地質環境に、性能に余裕をもたせた人工バリアを含む多重バリアシステムを構築する』というものである」と定義づけた。
この報告書については、高木学校と原子力資料情報室が組織した「地層処分問題研究グループ」が「『高レベル放射性廃棄物地層処分の技術的信頼性』批判」をまとめ、こう批判している。「多くの重要な事項について、恣意的な解釈と評価を行い、不確実さに対して科学的に真摯な検討を経ることなく、地層処分が行えるという予め定められた結論を導いている」。
しかし報告書の地層処分の定義は生き続け、こんなことをのたまう「専門家」まで現われるに至っている。「仮に適地の要件が200点満点だとする。調べたところ、地質は80点だったとしても、残る120点分は人工バリアで補うことができる」(長崎晋也東京大学大学院教授―2007年6月29日付電気新聞)。
今更ながら地層処分への道筋をたどってみれば、およそ信頼に足らないことは明白だろう。